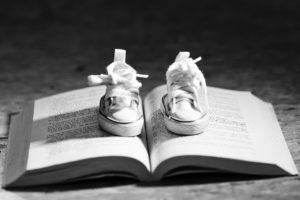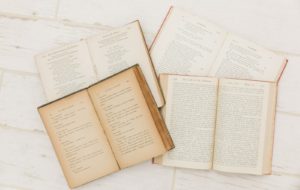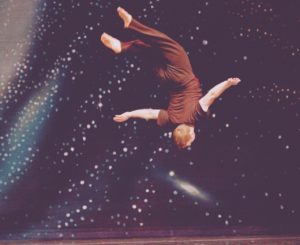[voice icon=”https://ekakisketch.com/wp-content/uploads/2017/12/ekakisketch_yukoprof_up-e1512269863485.jpg” name=”Yuko” type=”l”]おもしろかった本からひとつ!心理テストです〜〜[/voice]
発達心理学の本が結構おもしろくて、そこから心理テストをひとつ紹介します。
ちょっと考えさせられるテーマなので、ぜひぜひ。
[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”h3″ list_h2_type=”” list_h3_type=”” display=”” frame_design=”” animation=””]
ジレンマの発達心理学より
ちなみに、「心理テスト」というと身構えてしまって、判断基準がどっかよそ行きの選択になってしまうこともあります。無意識にも。
それは自分の中の「こうありたい」という理想の選択になっている、とも言えるのかなぁと。
さて、今回この問題の答えを見るのは、ちょっと勇気がいるかもです。
[voice icon=”https://ekakisketch.com/wp-content/uploads/2017/12/ekakisketch_yukoprof_up-e1512269863485.jpg” name=”Yuko” type=”l”]まずは何も考えずにこのストーリーを読んでくださいな。[/voice]
同じ村の、近所に住んでいるある夫婦がいた。
奥さんは癌に侵され、このままでは死んでしまう。妻をなんとか助けたい夫・・・。必死でなんとか手段はないかと奔走し、ついに隣町の薬剤師が治療薬を開発したという噂を耳にする。その薬剤師は開発費用の10倍の値段をつけた。
夫は1000ドルしか用意することが出来ない。薬剤師は2000ドルを要求している。夫は必死に頼み込む。
なんとかもっと安く売ってくれないか?後払いにしてくれないか?と。
しかし薬剤師の答えはNO。もうこれ以上交渉の余地はない。
失望した夫は、妻を助けるために薬剤師の店に押し入ってその薬を盗んだ。
あなたならどうしますか?
まさにジレンマ。難しいけれど少し考えてみましょ。
___では、彼の行動は正しかったのか?その理由もかならず考えてください
自分の考えを心の中にしっかりイメージしてみましょ。
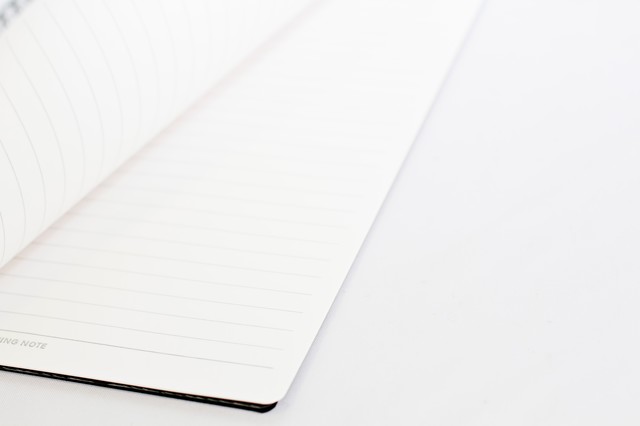
あなたの考えはどれに近いですか?
1)彼は薬を盗むべきではなかった。そんなことをしたら警察に捕まって刑務所行きだから。
2)薬を盗んでも彼には何の得にもならない。彼が刑務所から出てくる頃にはもう奥さんは死んでしまってるだろうから。
3)彼は薬を盗むべきではない。そんなことしたらみんなに犯罪者だと思われてしまうから。彼の奥さんだって盗んできた薬なんかで助かりたいと思わないはず。
4)たしかに彼の奥さんにはその薬が必要だけれど、法を犯してまでそれを手に入れようとするべきではない。奥さんが病気だからといって犯罪を正当化することは出来ない。
5)彼は薬を盗むべきではない。たしかに薬剤師のやり方はひどい。でも薬剤師にも報酬をもらう権利がある。お互いに相手のもつ権利を尊重するべきだ。
6)彼は薬を盗むべきだ。そして盗んだ後、自分のやったことをありのままに公表するべきだ。罰を受けなければならないことになっても、その代わりに人の命を救うことになる。
理由が大事!それぞれ少しずつだけど、その違いを意識して選択してください。
心理学者コールバーグ先生の診断結果
[voice icon=”https://ekakisketch.com/wp-content/uploads/2017/12/ekakisketch_yukoprof_up-e1512269863485.jpg” name=”Yuko” type=”l”]はい。準備はできたでしょうか?[/voice]
これは心理学者コールバーグさんの道徳性発達理論の中で、ジレンマに対する道徳的判断を元に、人間の道徳性の発達段階を示すもの。
それでは以下覚悟して読んでくださいね。
1)のような考え方の人は、懲罰志向といって権力に服従するタイプ
罰を受けるか、褒められるのかが重要で善悪の基準になっている。行為そのものの本質を見れてなく、自分の考え方ができていない段階。
2)のような考え方の人は、道徳的快楽志向といって褒美をもらえる場合に言うことを聞くタイプ
実利主義というか、交換条件を提示したり、見返りを求めるようなタイプ。相対的な損得が判断基準になっている。
3)のような考え方の人は、よい子志向といってまわりの人たちに喜ばれることがよい行動だとするタイプ
他人が喜ぶこと、助けること=善いこと。ここで初めて善に対する感覚があると言える。
他人の肯定や承認を重要視。多数決に従ったり、「当たり前のこと」「それが普通だから」という考えが主となっている。
4)のような考え方の人は、権威志向といって法律や秩序、権威を重視するタイプ
社会秩序を維持すること、ルールを守ることに強い忠誠心があり、義務感も感じるタイプ。
“すでに存在している” 社会秩序を維持することを善とし、乱すものを悪としている。
5)のような考え方の人は、社会契約志向といって、規則を絶対視するのではなく、正当な理由があればそれに代わる方法を主張するタイプ
ここから、目の前の行為ひとつひとつに対して判断しようと努力している。個人個人の権利を既存のルール、権力から独立して考えられる段階に入る。「人それぞれ」と考え、多様性も認めることができる。
6)のような考え方の人は、個人理念に基づく道徳性をもつ最高段階の道徳理念。自分で選択した普遍的な倫理があり、良心に従うタイプ
正義、公正、人間の尊厳、平等を重視し、何が正しいかを自分自身の倫理的基準がある。その倫理に従う良心をもつ人。例をあげると、イエス・キリスト、ブッダ、ガンジー、孔子、キング牧師など。
良心に従うので、法を超えて行動することができる。

5・6の段階は「脱慣習的段階」つまり「自分なりの答え」を出そうと努力する、固定観念からは独立した考え方ができる段階。
実際にこの段階にあたる人は全体の20%程度だろう、と。
解説のような文だとイマイチ入ってこないかもしれない。
でも6に例に出てくる偉人の名前を見ると、
あーそういうことか と納得できるんじゃないかな?
6はホント、偉人さん!!
ジレンマ・・・迷って悩んで、自分なりに考えれればいい
診断結果はどうだったかな?
人によってはちょっとショックだったりするかも。
自分のことを客観的に見つめることは勇気がいること。
しかも自分の価値観、コアな部分をぐさっとやられる。
ただこれは、あくまでも発達心理学という学問のひとつで、
「こういう見方も出来るよ」というアイディアのひとつであることはどうかお忘れなく。
[voice icon=”https://ekakisketch.com/wp-content/uploads/2017/12/ekakisketch_yukoprof_up-e1512269863485.jpg” name=”Yuko” type=”l”]他人を試すようにこの質問をして、人をジャッジしたりしないでくださいねー!![/voice]
自分を見つめるひとつの方法として。知ることはプラスになると思ってのご紹介でしたよ〜。
この心理テストが載っていた本はこちら↓
こういうジレンマ系のお話が好きな人には、ぜひ!この記事もおすすめしたい。
現代アーティスト スプツニ子!から投げかけられた生命の問いについても読んでみてください!
[box class=”pink_box” title=”合わせて読みたい”][kanren2 postid=”2444,2378″][/box]
とことん思考の海に溺れよう
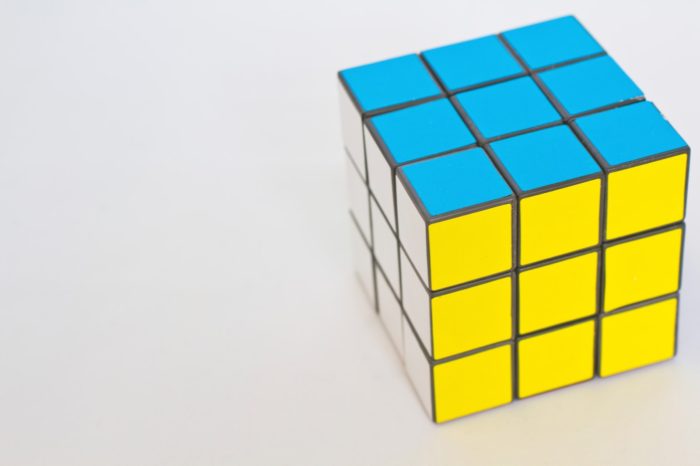
考えすぎると苦しくなる。
人生の中で大きな決断をするときは特に。
深い海の底のよう。
道を歩いてても、料理をしてても、シャワーを浴びてても、
夢の中でもつきまとう。
何をしててもその考え事が頭の中でぐるぐる。
こびりついて離れない。
それでも、考えるのはとっても良いことだと言えるよ。
本当に苦しかったとき「自分はなぜこうなんだろう?」
と思ったのがきっかけで、自分を観察するような感覚で
心理学の本をたくさん読むようになり。
その一つが発達心理学。
わたしは発達心理学のおかげでたくさん悩んで自分なりの答えを出そうとしていることはいいことなんだと思えて、
少し自信を持てるようになれた。
徐々に前向きに、前に進むことができました。
そうゆう小さい力になれたら嬉しいなと思いながら、このブログを更新しています。